2002─Ļ╚ššZę╗╝ēšµŅ}
Ģrķg:2005-4-3 20:21:30 ū„š▀:alex
ÕÅ»ÕÅ»Ķŗ▐p»Ł-“q┤ĶĮ╗õ║║ńÜäĶŗ▐p»ŁÕɼĶ»┤Ķ«Łń╗ā“qø_Å░
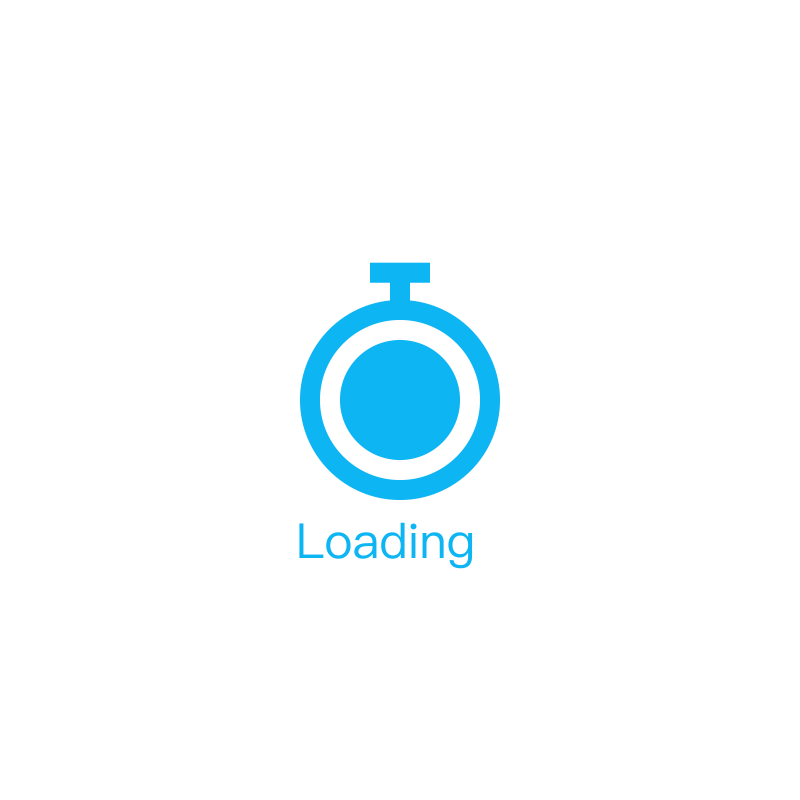
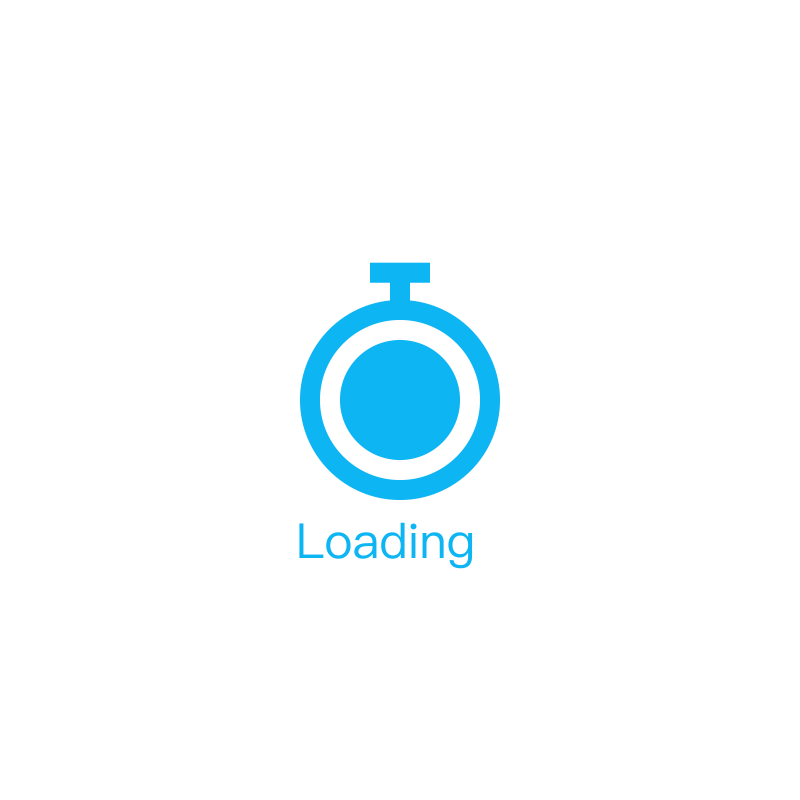
2002─Ļ╚ššZę╗╝ēšµŅ}
▒Šż“šiż▀ŠAż▒żŲżŌĪó├µ░ūż»ż╩żļż╚żŽż½ż«żķż╩żżĪŻ
ĪĪŻ▓ĪĪ┘Iż├ż┐▒Šż“║╬Č╚żŌšiżßżąĪóżĮż╬ü²éÄż¼Ęųż½żļżĶż”ż╦ż╩żļżŽż║ż└ĪŻ
ĪĪŻ│ĪĪšiĢ°ż╬├µ░ūżĄż“ų¬żļż┐żßż╦żŽĪóż▐ż║▒Šż“┘Iż├żŲ╔ĒĮ³ż╦ų├ż»ż│ż╚ż└ĪŻ
ĪĪŻ┤ĪĪ▒Šż╬├µ░ūżĄżŽ─Ļ²hż╦żĶż├żŲēõż’żļż╬żŪĪóąĪīW╔·ż½żķż╬šiĢ°ż¼┤¾Ūąż└ĪŻ
Ż©2Ż®┤¾īWż╬ųv┴xżõź╝ź▀ź╗®`źļż╬ł÷ż“═©żĘĪóš█ż╦żšżņĪó╦ĮżŽīW╔·ųTŠ²ż╦Ž“ż½ż├żŲĪóĪĖż╗ż├ż½ż»┤¾īWż╦╚ļż├ż┐ż╬ż└ż½żķĪóę╗ż─żŪżŌČÓż»ų¬Ą─Ėąäėż“╬Čż’żżĪóīWå¢ż“śSżĘż¾żŪż█żĘżżĪ╣ż╚šZżĻż½ż▒żŲżżżļĪŻ
ĪĪżĘż½żĘĪó¼F(xi©żn)ĀŅż“ęŖżŲżżżļż╚©D©D©DżŌż╚żĶżĻ╦Įż╬┴”▓╗ūŃżŌżóżĒż”ż¼©D©D©DÜł─Ņż╩ż¼żķĪóż│ż”żĘż┐źßź├ź╗®`źĖż¼╚¶żżųTŠ²ż╬ą─ż╦╩«ĘųĪóü╗ż’ż├żŲżżżļż╚żŽżżżżļyżżĪŻ▒╦żķż╬ż█ż╚ż¾ż╔ż╦ż╚ż├żŲśSżĘż▀ż╬īØŽ¾ż╚żżż©żąĪ󟥮`ź»źļ╗Ņäėżõź╣ź▌®`ź─Īó궜SĪóė│«ŗĪó┬■«ŗĪóżóżļżżżŽżĄż▐żČż▐ż╩źņźĖźŃ®`żŪżóżĻĪóżĮżņżķżŽżżż║żņżŌīWå¢ż╚żŽŠÓļxż“ų├żżż┐ż╚ż│żĒż╦żóżļż½żķżŪżóżļĪŻ
ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪó╦Įż¼╚šĪ®ĮėżĘżŲżżżļīW╔·ųTŠ²ż╦ż─żżżŲčįż©żąĪó▒╦żķż╬ČÓż»żŽøQżĘżŲīWśI(y©©)ż“ż¬żĒżĮż½ż╦żĘżŲżżżļż’ż▒żŪżŽż╩żżĪŻ▒╦żķżŽżĮżņż╩żĻż╦├ŃÅŖżĘĪóĖ▀żżīW┴”ż“│ųż├żŲżżżļż│ż╚żŽķg▀`żżż╩żżĪŻ
ĪĪż│ż”Ģ°ż»ż╚żżżĄżĄż½├¼Č▄żßż»żĶż”ż╦┬äż│ż©żļż½żŌżĘżņż╩żżż¼Īó┤¾ĘĮż╬īW╔·ż╦ż╚ż├żŲżŽīWå¢ż“śSżĘżÓą─ż╬ėÓįŻż“│ųż─ęįŪ░ż╦Īóż▐ż║żŽ─┐Ž╚ż╬─┐ś╦ż“Ēśż╦ż½ż┐ż┼ż▒ż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżż╚żżż”Ī░ÅŖŲ╚ėQ─ŅĪ▒ż“Ž╚ąąż╣żļż╬żŪżóżĒż”ĪŻŠ▀¾wĄ─ż╦żżż©żąĪóģg╬╗ż╬╚ĪĄ├Īó▀MīWĪóŠ═┬Üż╩ż╔īg└¹Ą─ż╩─┐ś╦ż╬▀_│╔ż¼ĪóĮ╣├╝ż╬╝▒ż╩ż╬żŪżóżļĪŻżĮżņżŽżĮżņżŪ╩╦ĘĮż╩żżż╬żŪżóżĒż”ż¼Īóż│ż╗ż│ż╗ż╗ż║ĪóżŌż”╔┘żĘŠ½╔±ż╬žNż½żĄż“żŌż├żŲīWå¢ż“ęŖż─żßų▒żĘĪó┤¾īW╔·╗Ņż“╦═ż├żŲżŌżķżżż┐żżż╚Īóż─żżūó╬─ż“ż─ż▒ż┐ż»ż╩żļĪŻ
å¢1ĪĪĪĖż│ż”żĘż┐źßź├ź╗®`źĖĪ╣ż╚żóżļż¼Īóż╔ż¾ż╩źßź├ź╗®`źĖż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪ┤¾īWż╦╚ļż├ż┐ż╬ż└ż½żķĪóīWå¢╔Žż╬ż¬żŌżĘżĒżĄż“ų¬ż├żŲż█żĘżżĪŻ
ĪĪŻ▓ĪĪ┤¾īWż╦╚ļż├ż┐ż╬ż└ż½żķĪóīWå¢ż╚żŽäeż╬śSżĘż▀żŌęŖż─ż▒żŲż█żĘżżĪŻ
ĪĪŻ│ĪĪ┤¾īWżŪż╬ūõśI(y©©)ż“ż¬żĒżĮż½ż╦żĘż╩żżżŪĪóĖ▀żżīW┴”ż“╔Ēż╦ż─ż▒żŲż█żĘżżĪŻ
Ż┤ĪĪ┤¾īWūõśI(y©©)ż╬ż┐żßż╦▒žę¬ż╩ģg╬╗ż“ż╚żĻĪóūįĘųż╬ŽŻ═¹ż“ż½ż╩ż©żŲż█żĘżżĪŻ
å¢2ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪż╬ųąż╦╚ļżļżŌż╬żŽż╔żņż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪżĮżņżµż©ĪĪĪĪĪĪĪĪŻ▓ĪĪż└ż½żķż│żĮĪĪĪĪĪĪŻ│ĪĪżĮżņż╔ż│żĒż½ĪĪĪĪŻ┤ĪĪż½ż╚żżż├żŲ
å¢3ĪĪĪĖżĮżņżŽżĮżņżŪ╩╦ĘĮż╩żżĪ╣ż╚żóżļż¼Īó║╬ż¼╩╦ĘĮż¼ż╩żżż╬ż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪīW╔·ż╦ü╗ż©ż┐żżūįĘųż╬╦╝żżż¼╩«Ęųü╗ż’żķż╩żżż│ż╚
ĪĪŻ▓ĪĪźĄ®`ź»źļ╗Ņäėżõź╣ź▌®`ź─ż“śSżĘż▀ż╬īØŽ¾ż╚ż╣żļż│ż╚
ĪĪŻ│ĪĪ─┐Ž╚ż╬─┐ś╦ż“ż½ż┐ż┼ż▒ż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżż╚żóż╗żļż│ż╚
ĪĪŻ┤ĪĪę╗ż─żŪżŌČÓż»Īóų¬Ą─Ėąäėż“╬Čż’żżĪóīWå¢ż“śSżĘżŌż”ż╚╦╝ż”ż│ż╚
å¢4ĪĪ╣Pš▀ż╦żĶżņżąĪó¼F(xi©żn)į┌ż╬ż█ż╚ż¾ż╔ż╬īW╔·ż╬─┐ś╦żŽ║╬ż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪŠ½╔±ż╬žNż½żĄż“żŌż├żŲīWå¢ż“ęŖż─żßż╩ż¬ż╣ż│ż╚
ĪĪŻ▓ĪĪżżżż│╔┐āż“╚Īż├żŲĪó▀MīWżóżļżżżŽŠ═┬Üż“╣¹ż┐ż╣ż│ż╚
ĪĪŻ│ĪĪźĄ®`ź»źļ╗Ņäėżõź╣ź▌®`ź─ż╩ż╔ż╦żĶżĻīWå¢ż╚ŠÓļxż“ų├ż»ż│ż╚
ĪĪŻ┤ĪĪūįĘųż╬źßź├ź╗®`źĖż“Īó╦¹ż╬╚╦ż╦╩«Ęųü╗ż’żļżĶż”ż╦ż╣żļż│ż╚
Ż©3Ż®╩└Įńż╬ųT├±ūÕż╬żóżżżĄż─ż“š{(di©żo)ż┘żŲż▀żļż╚ĪóŻ©ųą┬įŻ®╬š╩ųż╦┤·▒ĒżĄżņżļżĶż”ż╩ŽÓ╗źĄ─ż╩żóżżżĄż─żŽżŁż’żßżŲżßż║żķżĘżżż│ż╚ż¼żĶż»Ęųż½żļĪŻżĮżņżŽż┐żżżŲżżż╬╔ńĢ■żŪĪó╔ĒĘųżõĄž╬╗żõę█ĖŅż¼żŽż├żŁżĻČ©żßż├żŲżżżļż½żķż╦ż█ż½ż╩żķż╩żżĪŻż▐ż┐ĪóÜ░╚šż╬▌XżżżóżżżĄż─ż¼ż¬ż│ż╩ż’żņżļ╔ńĢ■ż¼╔┘ż╩żżż╚żżż”ż╬żŽĪóżĮżņżķż╬╔ńĢ■żŪżŽ╚╦żėż╚żŽżŌż├żčżķ╝ęūÕżõėHūÕżõ▓┐ūÕż╩ż╔╦∙ī┘ż╣żļ╔ńĢ■╝»ćŌż╬│╔åTż╚żĘżŲ╔·żŁżŲżżżŲĪóéĆ╚╦ż╚żĘżŲż╬ę█ĖŅż¼żóż▐żĻż▀ż╚żßżķżņżŲżżż╩żżż│ż╚ż╚ķvéSżĘżŲżżżļĪŻżĮż”żĘż┐╝»ćŌā╚(n©©i)żŪżŽĪó╬’ż╬żõżĻ╚ĪżĻż╩ż╔ż╬ļHż╦żŌĪóżšż─ż”żóżżżĄż─żŽżżżķż╩żżż╬żŪżóżļĪŻż┐ż╚ż©żąźżź¾ź╔żŪżŽ╝ęūÕżõėč╚╦ż╬żóżżż└żŪżŽżšż─ż”Ėąųxż╬▒Ē¼F(xi©żn)żŽż¬ż│ż╩ż’żņż╩żżĪŻż½ż©ż├żŲź┐źų®`ęĢżĄżņżļż╬ż└ż¼Īó╝ęūÕż╬╩│ū┐żŪēcż“╩ųČ╔żĘżŲżŌżķż├żŲżŌĪĖżóżĻż¼ż╚ż”Ī╣ż╚żżż”ÜW├ū┴„żŽĪó╝ęūÕż¼ę╗¾wż╦ż╩ż├żŲ─║żķż╣╔ńĢ■żŪżŽĪóżÓżĘżĒĪ░╦¹╚╦ąąāxĪ▒ż╩ż│ż╚ż╩ż╬ż└żĒż”ĪŻ
ĪĪ╚š▒Š╚╦żŌżżż─ż╬ż▐ż╦ż½╝ęūÕż╬ż╩ż½żŪĪĖżóżĻż¼ż╚ż”Ī╣ż“ż»żĻż½ż©ż╣żĶż”ż╦ż╩ż├ż┐ĪŻżĘż½żŌĪóżĮżņżŽ╬─Šõż╩żĘż╦żĶżż┴ĢæTż╚ż½ż¾ż¼ż©żķżņżŲżżżļżĶż”ż└ĪŻżĮżņżŽ╝ęūÕż¼╔Ēż“╝─ż╗║Žż”żĶż”ż╦żĘżŲ╔·żŁżŲżżż┐─║żķżĘż¼ż╣ż├ż½żĻ▀^╚źż╬żŌż╬ż╦ż╩żĻĪó╚╦ķgķvéSż¼śöēõż’żĻżĘż┐ż│ż╚ż“╚ńīgż╦╬’šZż├żŲżżżļĪŻ
å¢1ĪĪĪĖŽÓ╗źĄ─ż╩żóżżżĄż─żŽżŁż’żßżŲżßż║żķżĘżżĪ╣ż╚żóżļż¼Īóż╩ż╝ż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪČÓż»ż╬╔ńĢ■żŪżŽĪó╚╦Ī®ż╬╔ĒĘųżõę█ĖŅż¼żŁż▐ż├żŲżżżļż½żķ
ĪĪŻ▓ĪĪ╔ĒĘųżõĄž╬╗ż╦ķvéSż╩ż»Īó╬š╩ųż¼┤·▒ĒĄ─ż╩żóżżżĄż─ż└ż½żķ
ĪĪŻ│ĪĪÜ░╚šż╬▌XżżżóżżżĄż─ż¼ż¬ż│ż╩ż’żņżļż╬ż¼Īóżóż┐żĻż▐ż©ż└ż½żķ
ĪĪŻ┤ĪĪ╩└Įńż╬ųT├±ūÕżŪżŽĪó╔ĒĘųżõę█ĖŅż¼ż▐ż└żŽż├żŁżĻČ©ż▐ż├żŲżżż╩żżż½żķ
å¢2ĪĪźżź¾ź╔ż╦ż─żżżŲż╬šh├„ż╚żĘżŲš²żĘżżżŌż╬żŽż╔żņż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪéĆ╚╦ż╚żĘżŲż╬ę█ĖŅż¼ż▀ż╚żßżķżņżŲżżżļż╬żŪĪóżšż─ż”╝ęūÕż╦ĪĖżóżĻż¼ż╚ż”Ī╣ż╚čįż’ż╩żżĪŻ
ĪĪŻ▓ĪĪ╝ęūÕż╬╩│ū┐żŪēcż“╩ųČ╔żĘżŲżŌżķż├żŲĖąųxż╬▒Ē¼F(xi©żn)ż“╩╣ż’ż╩żżż│ż╚żŽĪóź┐źų®`ęĢżĄżņżļĪŻ
ĪĪŻ│ĪĪ╝ęūÕżõėHūÕż╩ż╔ż╬╔ńĢ■╝»ćŌż╬│╔åT═¼╩┐ż╬ķgżŪżŽĪóĖąųxż╬▒Ē¼F(xi©żn)ż¼żĶż»╩╣ż’żņżļĪŻ
ĪĪŻ┤ĪĪ╝ęūÕż¼ę╗¾wż╚ż╩ż├żŲ─║żķż╣╔ńĢ■ż╩ż╬żŪĪóżóż▐żĻĪĖżóżĻż¼ż╚ż”Ī╣ż╚čįż’ż╩żżĪŻ
å¢3ĪĪ╚š▒Šż╦ż─żżżŲż╬šh├„ż╚żĘżŲš²żĘżżżŌż╬żŽż╔żņż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪĪĖżóżĻż¼ż╚ż”Ī╣ż¼żĶżż┴ĢæTż╚┐╝ż©żķżņżļż╬żŽĪó╚╦ķgķvéSż¼ż½ż’ż├żŲéĆ╚╦ż╚żĘżŲż╬ę█ĖŅż¼żóż▐żĻż▀ż╚żßżķżņżŲżżż╩żżż½żķżŪżóżļĪŻ
ĪĪŻ▓ĪĪż½ż─żŲżŽ╝ę═źż╬ųążŪĖąųxż╬▒Ē¼F(xi©żn)żŽżóż▐żĻ╩╣ż’żņż╩ż½ż├ż┐ż¼ĪóūŅĮ³żŽżĶżż┴ĢæTż╚┐╝ż©żķżņżŲŅlĘ▒ż╦╩╣ż’żņżļĪŻ
ĪĪŻ│ĪĪ╬¶ż½żķ╝ę═źż╬ųążŪżŽĖąųxż╬čį╚~ż¼żĶż»╩╣ż’żņżŲżżż┐ż¼ĪóūŅĮ³żŽ╬─Šõż╩żĘż╬żĶżż┴ĢæTż╚żĘżŲČ©ų°żĘżŲżżżļĪŻ
ĪĪŻ┤ĪĪ╝ę═źż╬ųążŪĖąųxż╬čį╚~ż¼żĶż»╩╣ż’żņżļż╬żŽĪó╝ęūÕż¼╔Ēż“╝─ż╗║Žż”żĶż”ż╦żĘżŲ─║żķżĘżŲżżżļż½żķżŪżóżļĪŻ
å¢Ņ}ó¾ĪĪ┤╬ż╬Ż©1Ż®ż½żķŻ©4Ż®ż╬╬─š┬ż“šiż¾żŪĪóżĮżņżŠżņż╬å¢żżż╦īØż╣żļ┤ż©ż╚żĘżŲūŅżŌ▀m«öż╩żŌż╬ż“1・2・3・4ż½żķę╗ż─▀xżėż╩żĄżżĪŻ
Ż©1Ż®ęįŪ░ż╬ż│ż╚żŪż╣
▒Šż“šiż▀ŠAż▒żŲżŌĪó├µ░ūż»ż╩żļż╚żŽż½ż«żķż╩żżĪŻ
ĪĪŻ▓ĪĪ┘Iż├ż┐▒Šż“║╬Č╚żŌšiżßżąĪóżĮż╬ü²éÄż¼Ęųż½żļżĶż”ż╦ż╩żļżŽż║ż└ĪŻ
ĪĪŻ│ĪĪšiĢ°ż╬├µ░ūżĄż“ų¬żļż┐żßż╦żŽĪóż▐ż║▒Šż“┘Iż├żŲ╔ĒĮ³ż╦ų├ż»ż│ż╚ż└ĪŻ
ĪĪŻ┤ĪĪ▒Šż╬├µ░ūżĄżŽ─Ļ²hż╦żĶż├żŲēõż’żļż╬żŪĪóąĪīW╔·ż½żķż╬šiĢ°ż¼┤¾Ūąż└ĪŻ
Ż©2Ż®┤¾īWż╬ųv┴xżõź╝ź▀ź╗®`źļż╬ł÷ż“═©żĘĪóš█ż╦żšżņĪó╦ĮżŽīW╔·ųTŠ²ż╦Ž“ż½ż├żŲĪóĪĖż╗ż├ż½ż»┤¾īWż╦╚ļż├ż┐ż╬ż└ż½żķĪóę╗ż─żŪżŌČÓż»ų¬Ą─Ėąäėż“╬Čż’żżĪóīWå¢ż“śSżĘż¾żŪż█żĘżżĪ╣ż╚šZżĻż½ż▒żŲżżżļĪŻ
ĪĪżĘż½żĘĪó¼F(xi©żn)ĀŅż“ęŖżŲżżżļż╚©D©D©DżŌż╚żĶżĻ╦Įż╬┴”▓╗ūŃżŌżóżĒż”ż¼©D©D©DÜł─Ņż╩ż¼żķĪóż│ż”żĘż┐źßź├ź╗®`źĖż¼╚¶żżųTŠ²ż╬ą─ż╦╩«ĘųĪóü╗ż’ż├żŲżżżļż╚żŽżżżżļyżżĪŻ▒╦żķż╬ż█ż╚ż¾ż╔ż╦ż╚ż├żŲśSżĘż▀ż╬īØŽ¾ż╚żżż©żąĪ󟥮`ź»źļ╗Ņäėżõź╣ź▌®`ź─Īó궜SĪóė│«ŗĪó┬■«ŗĪóżóżļżżżŽżĄż▐żČż▐ż╩źņźĖźŃ®`żŪżóżĻĪóżĮżņżķżŽżżż║żņżŌīWå¢ż╚żŽŠÓļxż“ų├żżż┐ż╚ż│żĒż╦żóżļż½żķżŪżóżļĪŻ
ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪó╦Įż¼╚šĪ®ĮėżĘżŲżżżļīW╔·ųTŠ²ż╦ż─żżżŲčįż©żąĪó▒╦żķż╬ČÓż»żŽøQżĘżŲīWśI(y©©)ż“ż¬żĒżĮż½ż╦żĘżŲżżżļż’ż▒żŪżŽż╩żżĪŻ▒╦żķżŽżĮżņż╩żĻż╦├ŃÅŖżĘĪóĖ▀żżīW┴”ż“│ųż├żŲżżżļż│ż╚żŽķg▀`żżż╩żżĪŻ
ĪĪż│ż”Ģ°ż»ż╚żżżĄżĄż½├¼Č▄żßż»żĶż”ż╦┬äż│ż©żļż½żŌżĘżņż╩żżż¼Īó┤¾ĘĮż╬īW╔·ż╦ż╚ż├żŲżŽīWå¢ż“śSżĘżÓą─ż╬ėÓįŻż“│ųż─ęįŪ░ż╦Īóż▐ż║żŽ─┐Ž╚ż╬─┐ś╦ż“Ēśż╦ż½ż┐ż┼ż▒ż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżż╚żżż”Ī░ÅŖŲ╚ėQ─ŅĪ▒ż“Ž╚ąąż╣żļż╬żŪżóżĒż”ĪŻŠ▀¾wĄ─ż╦żżż©żąĪóģg╬╗ż╬╚ĪĄ├Īó▀MīWĪóŠ═┬Üż╩ż╔īg└¹Ą─ż╩─┐ś╦ż╬▀_│╔ż¼ĪóĮ╣├╝ż╬╝▒ż╩ż╬żŪżóżļĪŻżĮżņżŽżĮżņżŪ╩╦ĘĮż╩żżż╬żŪżóżĒż”ż¼Īóż│ż╗ż│ż╗ż╗ż║ĪóżŌż”╔┘żĘŠ½╔±ż╬žNż½żĄż“żŌż├żŲīWå¢ż“ęŖż─żßų▒żĘĪó┤¾īW╔·╗Ņż“╦═ż├żŲżŌżķżżż┐żżż╚Īóż─żżūó╬─ż“ż─ż▒ż┐ż»ż╩żļĪŻ
å¢1ĪĪĪĖż│ż”żĘż┐źßź├ź╗®`źĖĪ╣ż╚żóżļż¼Īóż╔ż¾ż╩źßź├ź╗®`źĖż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪ┤¾īWż╦╚ļż├ż┐ż╬ż└ż½żķĪóīWå¢╔Žż╬ż¬żŌżĘżĒżĄż“ų¬ż├żŲż█żĘżżĪŻ
ĪĪŻ▓ĪĪ┤¾īWż╦╚ļż├ż┐ż╬ż└ż½żķĪóīWå¢ż╚żŽäeż╬śSżĘż▀żŌęŖż─ż▒żŲż█żĘżżĪŻ
ĪĪŻ│ĪĪ┤¾īWżŪż╬ūõśI(y©©)ż“ż¬żĒżĮż½ż╦żĘż╩żżżŪĪóĖ▀żżīW┴”ż“╔Ēż╦ż─ż▒żŲż█żĘżżĪŻ
Ż┤ĪĪ┤¾īWūõśI(y©©)ż╬ż┐żßż╦▒žę¬ż╩ģg╬╗ż“ż╚żĻĪóūįĘųż╬ŽŻ═¹ż“ż½ż╩ż©żŲż█żĘżżĪŻ
å¢2ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪż╬ųąż╦╚ļżļżŌż╬żŽż╔żņż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪżĮżņżµż©ĪĪĪĪĪĪĪĪŻ▓ĪĪż└ż½żķż│żĮĪĪĪĪĪĪŻ│ĪĪżĮżņż╔ż│żĒż½ĪĪĪĪŻ┤ĪĪż½ż╚żżż├żŲ
å¢3ĪĪĪĖżĮżņżŽżĮżņżŪ╩╦ĘĮż╩żżĪ╣ż╚żóżļż¼Īó║╬ż¼╩╦ĘĮż¼ż╩żżż╬ż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪīW╔·ż╦ü╗ż©ż┐żżūįĘųż╬╦╝żżż¼╩«Ęųü╗ż’żķż╩żżż│ż╚
ĪĪŻ▓ĪĪźĄ®`ź»źļ╗Ņäėżõź╣ź▌®`ź─ż“śSżĘż▀ż╬īØŽ¾ż╚ż╣żļż│ż╚
ĪĪŻ│ĪĪ─┐Ž╚ż╬─┐ś╦ż“ż½ż┐ż┼ż▒ż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżż╚żóż╗żļż│ż╚
ĪĪŻ┤ĪĪę╗ż─żŪżŌČÓż»Īóų¬Ą─Ėąäėż“╬Čż’żżĪóīWå¢ż“śSżĘżŌż”ż╚╦╝ż”ż│ż╚
å¢4ĪĪ╣Pš▀ż╦żĶżņżąĪó¼F(xi©żn)į┌ż╬ż█ż╚ż¾ż╔ż╬īW╔·ż╬─┐ś╦żŽ║╬ż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪŠ½╔±ż╬žNż½żĄż“żŌż├żŲīWå¢ż“ęŖż─żßż╩ż¬ż╣ż│ż╚
ĪĪŻ▓ĪĪżżżż│╔┐āż“╚Īż├żŲĪó▀MīWżóżļżżżŽŠ═┬Üż“╣¹ż┐ż╣ż│ż╚
ĪĪŻ│ĪĪźĄ®`ź»źļ╗Ņäėżõź╣ź▌®`ź─ż╩ż╔ż╦żĶżĻīWå¢ż╚ŠÓļxż“ų├ż»ż│ż╚
ĪĪŻ┤ĪĪūįĘųż╬źßź├ź╗®`źĖż“Īó╦¹ż╬╚╦ż╦╩«Ęųü╗ż’żļżĶż”ż╦ż╣żļż│ż╚
Ż©3Ż®╩└Įńż╬ųT├±ūÕż╬żóżżżĄż─ż“š{(di©żo)ż┘żŲż▀żļż╚ĪóŻ©ųą┬įŻ®╬š╩ųż╦┤·▒ĒżĄżņżļżĶż”ż╩ŽÓ╗źĄ─ż╩żóżżżĄż─żŽżŁż’żßżŲżßż║żķżĘżżż│ż╚ż¼żĶż»Ęųż½żļĪŻżĮżņżŽż┐żżżŲżżż╬╔ńĢ■żŪĪó╔ĒĘųżõĄž╬╗żõę█ĖŅż¼żŽż├żŁżĻČ©żßż├żŲżżżļż½żķż╦ż█ż½ż╩żķż╩żżĪŻż▐ż┐ĪóÜ░╚šż╬▌XżżżóżżżĄż─ż¼ż¬ż│ż╩ż’żņżļ╔ńĢ■ż¼╔┘ż╩żżż╚żżż”ż╬żŽĪóżĮżņżķż╬╔ńĢ■żŪżŽ╚╦żėż╚żŽżŌż├żčżķ╝ęūÕżõėHūÕżõ▓┐ūÕż╩ż╔╦∙ī┘ż╣żļ╔ńĢ■╝»ćŌż╬│╔åTż╚żĘżŲ╔·żŁżŲżżżŲĪóéĆ╚╦ż╚żĘżŲż╬ę█ĖŅż¼żóż▐żĻż▀ż╚żßżķżņżŲżżż╩żżż│ż╚ż╚ķvéSżĘżŲżżżļĪŻżĮż”żĘż┐╝»ćŌā╚(n©©i)żŪżŽĪó╬’ż╬żõżĻ╚ĪżĻż╩ż╔ż╬ļHż╦żŌĪóżšż─ż”żóżżżĄż─żŽżżżķż╩żżż╬żŪżóżļĪŻż┐ż╚ż©żąźżź¾ź╔żŪżŽ╝ęūÕżõėč╚╦ż╬żóżżż└żŪżŽżšż─ż”Ėąųxż╬▒Ē¼F(xi©żn)żŽż¬ż│ż╩ż’żņż╩żżĪŻż½ż©ż├żŲź┐źų®`ęĢżĄżņżļż╬ż└ż¼Īó╝ęūÕż╬╩│ū┐żŪēcż“╩ųČ╔żĘżŲżŌżķż├żŲżŌĪĖżóżĻż¼ż╚ż”Ī╣ż╚żżż”ÜW├ū┴„żŽĪó╝ęūÕż¼ę╗¾wż╦ż╩ż├żŲ─║żķż╣╔ńĢ■żŪżŽĪóżÓżĘżĒĪ░╦¹╚╦ąąāxĪ▒ż╩ż│ż╚ż╩ż╬ż└żĒż”ĪŻ
ĪĪ╚š▒Š╚╦żŌżżż─ż╬ż▐ż╦ż½╝ęūÕż╬ż╩ż½żŪĪĖżóżĻż¼ż╚ż”Ī╣ż“ż»żĻż½ż©ż╣żĶż”ż╦ż╩ż├ż┐ĪŻżĘż½żŌĪóżĮżņżŽ╬─Šõż╩żĘż╦żĶżż┴ĢæTż╚ż½ż¾ż¼ż©żķżņżŲżżżļżĶż”ż└ĪŻżĮżņżŽ╝ęūÕż¼╔Ēż“╝─ż╗║Žż”żĶż”ż╦żĘżŲ╔·żŁżŲżżż┐─║żķżĘż¼ż╣ż├ż½żĻ▀^╚źż╬żŌż╬ż╦ż╩żĻĪó╚╦ķgķvéSż¼śöēõż’żĻżĘż┐ż│ż╚ż“╚ńīgż╦╬’šZż├żŲżżżļĪŻ
å¢1ĪĪĪĖŽÓ╗źĄ─ż╩żóżżżĄż─żŽżŁż’żßżŲżßż║żķżĘżżĪ╣ż╚żóżļż¼Īóż╩ż╝ż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪČÓż»ż╬╔ńĢ■żŪżŽĪó╚╦Ī®ż╬╔ĒĘųżõę█ĖŅż¼żŁż▐ż├żŲżżżļż½żķ
ĪĪŻ▓ĪĪ╔ĒĘųżõĄž╬╗ż╦ķvéSż╩ż»Īó╬š╩ųż¼┤·▒ĒĄ─ż╩żóżżżĄż─ż└ż½żķ
ĪĪŻ│ĪĪÜ░╚šż╬▌XżżżóżżżĄż─ż¼ż¬ż│ż╩ż’żņżļż╬ż¼Īóżóż┐żĻż▐ż©ż└ż½żķ
ĪĪŻ┤ĪĪ╩└Įńż╬ųT├±ūÕżŪżŽĪó╔ĒĘųżõę█ĖŅż¼ż▐ż└żŽż├żŁżĻČ©ż▐ż├żŲżżż╩żżż½żķ
å¢2ĪĪźżź¾ź╔ż╦ż─żżżŲż╬šh├„ż╚żĘżŲš²żĘżżżŌż╬żŽż╔żņż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪéĆ╚╦ż╚żĘżŲż╬ę█ĖŅż¼ż▀ż╚żßżķżņżŲżżżļż╬żŪĪóżšż─ż”╝ęūÕż╦ĪĖżóżĻż¼ż╚ż”Ī╣ż╚čįż’ż╩żżĪŻ
ĪĪŻ▓ĪĪ╝ęūÕż╬╩│ū┐żŪēcż“╩ųČ╔żĘżŲżŌżķż├żŲĖąųxż╬▒Ē¼F(xi©żn)ż“╩╣ż’ż╩żżż│ż╚żŽĪóź┐źų®`ęĢżĄżņżļĪŻ
ĪĪŻ│ĪĪ╝ęūÕżõėHūÕż╩ż╔ż╬╔ńĢ■╝»ćŌż╬│╔åT═¼╩┐ż╬ķgżŪżŽĪóĖąųxż╬▒Ē¼F(xi©żn)ż¼żĶż»╩╣ż’żņżļĪŻ
ĪĪŻ┤ĪĪ╝ęūÕż¼ę╗¾wż╚ż╩ż├żŲ─║żķż╣╔ńĢ■ż╩ż╬żŪĪóżóż▐żĻĪĖżóżĻż¼ż╚ż”Ī╣ż╚čįż’ż╩żżĪŻ
å¢3ĪĪ╚š▒Šż╦ż─żżżŲż╬šh├„ż╚żĘżŲš²żĘżżżŌż╬żŽż╔żņż½ĪŻ
ĪĪŻ▒ĪĪĪĖżóżĻż¼ż╚ż”Ī╣ż¼żĶżż┴ĢæTż╚┐╝ż©żķżņżļż╬żŽĪó╚╦ķgķvéSż¼ż½ż’ż├żŲéĆ╚╦ż╚żĘżŲż╬ę█ĖŅż¼żóż▐żĻż▀ż╚żßżķżņżŲżżż╩żżż½żķżŪżóżļĪŻ
ĪĪŻ▓ĪĪż½ż─żŲżŽ╝ę═źż╬ųążŪĖąųxż╬▒Ē¼F(xi©żn)żŽżóż▐żĻ╩╣ż’żņż╩ż½ż├ż┐ż¼ĪóūŅĮ³żŽżĶżż┴ĢæTż╚┐╝ż©żķżņżŲŅlĘ▒ż╦╩╣ż’żņżļĪŻ
ĪĪŻ│ĪĪ╬¶ż½żķ╝ę═źż╬ųążŪżŽĖąųxż╬čį╚~ż¼żĶż»╩╣ż’żņżŲżżż┐ż¼ĪóūŅĮ³żŽ╬─Šõż╩żĘż╬żĶżż┴ĢæTż╚żĘżŲČ©ų°żĘżŲżżżļĪŻ
ĪĪŻ┤ĪĪ╝ę═źż╬ųążŪĖąųxż╬čį╚~ż¼żĶż»╩╣ż’żņżļż╬żŽĪó╝ęūÕż¼╔Ēż“╝─ż╗║Žż”żĶż”ż╦żĘżŲ─║żķżĘżŲżżżļż½żķżŪżóżļĪŻ
å¢Ņ}ó¾ĪĪ┤╬ż╬Ż©1Ż®ż½żķŻ©4Ż®ż╬╬─š┬ż“šiż¾żŪĪóżĮżņżŠżņż╬å¢żżż╦īØż╣żļ┤ż©ż╚żĘżŲūŅżŌ▀m«öż╩żŌż╬ż“1・2・3・4ż½żķę╗ż─▀xżėż╩żĄżżĪŻ
Ż©1Ż®ęįŪ░ż╬ż│ż╚żŪż╣


