2000─Ļ╚ššZę╗╝ēšµŅ}╝░┤░Ė
Ģrķg:2005-4-3 20:18:37 ū„š▀:alex
ÕÅ»ÕÅ»Ķŗ▐p»Ł-“q┤ĶĮ╗õ║║ńÜäĶŗ▐p»ŁÕɼĶ»┤Ķ«Łń╗ā“qø_Å░
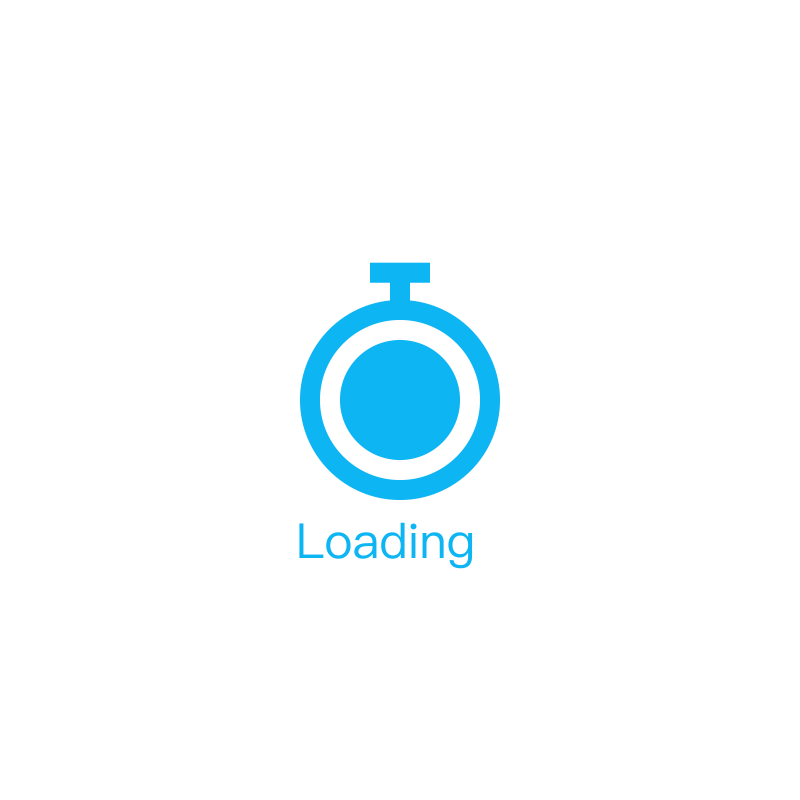
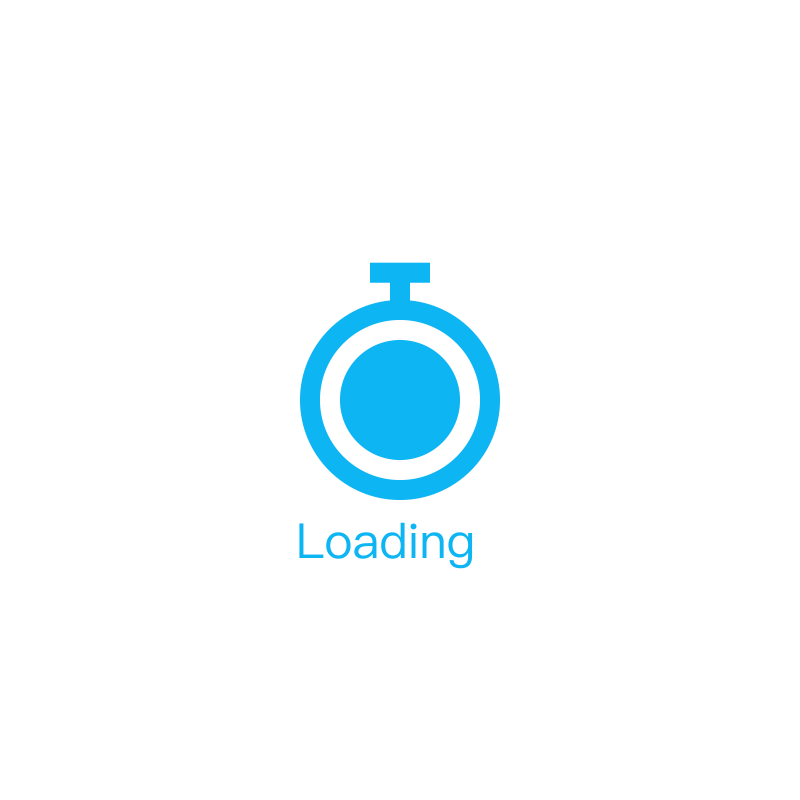
2000─Ļ╚ššZę╗╝ēšµŅ}╝░┤░Ė
żŲĪó「╩▄“YæķĀÄ」ż“┐ŽČ©ż╣żļÜ▌żŽż╩żżĪŻŻ©ųą┬įŻ®▀^┐ßż╩「╩▄“YæķĀÄ」ż╦żŽžōż╬é╚├µż¼ČÓżżż╬żŪĪóæķĀÄż“ż╩ż»ż╣żļ▒žę¬ąįżŽĖ▀żżĪŻĪĪż╚ż│żĒżŪĪó╠žČ©┤¾īWęį═Ōż╬īW╔·ż╦ż╚ż├żŲżŽĪóŠ═┬Üįć“Yż╬ÖCĢ■ż¼ūŅ│§ż½żķ┼┼│²żĄżņżŲżżżļż╬żŪĪóÖCĢ■ż╬▓╗ŲĮĄ╚ż╚ė│żļż½żŌżĘżņż╩żżĪŻ┤_ż½ż╦żĮż╬é╚├µż¼żóżļż│ż╚żŽĘ±Č©żĘż©ż╩żżż¼ĪóżĶż»┐╝ż©żļż╚żĮż╬╚╦▀_ż╦żŌ╠žČ©ż╬┤¾īWż╬╩▄“Yż╬ÖCĢ■ż¼Ė▀ąŻ╔·ż╬Ģrż╦żóż├ż┐ż’ż▒żŪĪóÖCĢ■ż╬ŲĮĄ╚ż¼═Ļ╚½ż╦┼┼│²żĄżņżŲżżż┐ż╚żŽżżż©ż╩żżĪŻīgļHż╦żĮż╬┤¾īWż“╩▄“YżĘż┐ż½ż╔ż”ż½żŽå¢Ņ}żŪżŽż╩żżĪŻżĘż½żĘĖ▀ąŻ╔·ż╦ż▐żŪŲ¾śIż╦ųĖČ©ąŻųŲČ╚ż¼żóżļż│ż╚ż“ų¬ż├żŲżżżļĪóż╚Ų┌┤²ż╣żļż╬żŽ┐ßżŪżóżļĪŻÖCĢ■ż╬ŲĮĄ╚ż“ż│ż╬żĶż”ż╦┐╝ż©żŲż▀żļż╚ĪóęŌ═Ōż╦č}ļjż╩įŁ└Ēż╩ż╬żŪżóżļĪŻĪĪÖCĢ■Š∙Ą╚ż╬įŁ└Ēż“īg╩®ż╣żļż│ż╚żŽ╚▌ęūżŪżŽż╩żżż¼Īó└ĒŽļż╚żĘżŲ│Żż╦─ŅŅ^ż╬ż¬ż½żņżļż┘żŁįŁ└ĒżŪżóżļĪŻż╣ż┘żŲż╬ęŌė¹ż╬żóżļ╚╦ż╦żŽĪóģó╝ėż╚ĖéĀÄż╬ÖCĢ■ż¼┼cż©żķżņżļż│ż╚ż¼═¹ż▐żĘżżĪŻĮ╠ė²ż╬ÖCĢ■Īó╩╦╩┬ż╬ÖCĢ■ĪóŠ═┬Üż╬ÖCĢ■ĪóĢN▀Mż╬ÖCĢ■Īó╚╦╔·╔Žż╬śöśöż╩╗Ņäėż╦ż¬żżżŲČÓż»ż╬╚╦ż╦ŲĮĄ╚ż╩ÖCĢ■ż¼┼cż©żķżņż┐─®ż╦Īóģó╝ėš▀ż¼Ėéżż║Žż”ż│ż╚ż╚ż╩żļĪŻĖéĀÄż╬ĮY╣¹ä┘š▀ż╚öĪš▀ż¼│÷żļż│ż╚żŽ╩╦ĘĮż¼ż╩żżż│ż╚ż└żĘĪóä┘š▀ż╦żŌĒś╬╗ż┼ż▒ż¼ąąż’żņżļż│ż╚żŌżõżÓż“ż©ż╩żżĪŻ å¢1ĪĪĄ┌2Č╬┬õż╬ā╚╚▌ż╚║Žż├żŲżżżļżŌż╬żŽĪóż╔żņż½ĪŻ 1 ╚š▒ŠżŪżŽėHż╬ĮU£g┴”ż¼Ė▀ż»ż╩żżż┐żßż╦ūė╣®ż¼▀MīWżŪżŁż╩żżź▒®`ź╣żŽ£pż├żŲżŁżŲżżżļĪŻ 2 ╚š▒ŠżŪżŽėHż╬ĮU£g┴”ż¼Ė▀ż»ż╩żżż┐żßż╦ūė╣®ż¼▀MīWżŪżŁż╩żżź▒®`ź╣ż¼ę└╚╗ż╚żĘżŲČÓżżĪŻ 3 źóźßźĻź½żŪżŽÖCĢ■ż╬ŲĮĄ╚ż¼ųžęĢżĄżņżļż¼ĪóŖXīWĮųŲČ╚żŽ╚š▒Šż█ż╔│õīgżĘżŲżżż╩żżĪŻ 4 źóźßźĻź½żŪżŽÖCĢ■ż╬ŲĮĄ╚ż¼╚š▒Šż█ż╔ųžęĢżĄżņż╩żżż¼ĪóŖXīWĮųŲČ╚żŽ│õīgżĘżŲżżżļĪŻå¢2ĪĪųĖČ©ąŻųŲČ╚ż╬╠žÅšż╚żĘżŲĪó╣Pš▀ż╬šh├„ż╚║Žż”żŌż╬żŽż╔żņż½ĪŻ 1 ╠žČ©ż╬┤¾īWż╬ūõśI╔·ż└ż▒ż¼żĮż╬Ų¾śIżŪāPż»żĶż”ż╦ż╩żļż┐żßĪóŲ¾śIż╦īØżĘżŲųęīgż╩╔ńåTż“ēłżõż╣ż│ż╚ż¼żŪżŁżļĪŻ 2 ČÓż»ż╬īW╔·ż╬ųąż½żķ▀xżųż│ż╚ż╦ż╩żļż┐żßĪóŲ¾śIżŽ╚ļ╔ńßßż╣ż░ż╦│╔╣¹ż“╔Žż▓żķżņżļ╚╦ż“ęŖż─ż▒żļż│ż╚ż¼żŪżŁżļĪŻ 3 ╠žČ©ż╬┤¾īWęį═Ōż╬īW╔·żŽĪóÅĻ─╝ż╣żļļHż╦įć“Yż“╩▄ż▒ż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżż┐żßĪóę╗Č©ż╬╗∙£╩ęį╔Žż╬╚╦ż“▀xżųż│ż╚ż¼żŪżŁżļĪŻ 4 ā׹ѿ╩īW╔·ż¼żżżļż╚┐╝ż©żķżņżļ┤¾īWż╬īW╔·ż└ż▒ż¼ÅĻ─╝żŪżŁżļż┐żßĪóŲ¾śIżŽĄ═żżź│ź╣ź╚żŪ▀m«öż╩╚╦ż“▀xżųż│ż╚ż¼żŪżŁżļĪŻå¢3ĪĪĪĖżĮż╬╚╦▀_Ī╣ż╚żŽĪóż╔ż╬żĶż”ż╩╚╦ż“ųĖżĘżŲżżżļż½ĪŻ 1ĪĪ┤¾īW╩┌śIż“żĘż╩ż½ż├ż┐Ė▀ąŻ╔· 2ĪĪŲ¾śIż╬Ʊė├įć“Yż╦ÅĻ─╝żĘżŲż»żļż╣ż┘żŲż╬īW╔· 3 Ų¾śIż¼╩▄“Y・├µĮėż╬ÖCĢ■ż“┼cż©żŲżżż╩żż┤¾īWż╬īW╔· 4 Ų¾śIż¼╩▄“Y・├µĮėż╬ÖCĢ■ż“┼cż©żŲżżżļ╠žČ©┤¾īWż╬īW╔·å¢4ĪĪĖ▀ąŻż╬ļAČ╬ż╦ż▐żŪżĄż½ż╬ż▄ż├żŲ┐╝ż©ż┐ł÷║ŽĪóųĖČ©ąŻųŲČ╚ż╚ÖCĢ■ż╬ŲĮĄ╚ż╦ż─żżżŲ╣Pš▀żŽż╔ż╬żĶż”ż╦įuü²żĘżŲżżżļż½ĪŻ 1 Ė▀ąŻ╔·ż¼ųĖČ©ąŻųŲČ╚ż¼ż╩ż»ż╩żļż│ż╚ż“Ų┌┤²ż╣żļżŽż║ż¼ż╩żżż½żķĪóÖCĢ■ż╬▓╗ŲĮĄ╚żŽżĮżņż█ż╔┤¾żŁż╩å¢Ņ}żŪżŽż╩żżĪŻ 2 Ė▀ąŻ╔·żŽųĖČ©ąŻųŲČ╚ż¼żóżļż│ż╚ż“ų¬ż├ż┐ż”ż©żŪ┤¾īWż“╩▄“YżĘżŲżżżļż╬ż└ż½żķĪóÖCĢ■ż╬▓╗ŲĮĄ╚żŽżĮżņż█ż╔┤¾żŁż╩å¢Ņ}żŪżŽż╩żżĪŻ 3 ż╔ż¾ż╩Ė▀ąŻ╔·żŪżŌųĖČ©ąŻż╬┤¾īWż“╩▄“Yż╣żļż│ż╚żŽżŪżŁżļż¼Īóż╣ż┘żŲż╬╩▄“Y╔·ż¼║ŽĖ±żŪżŁżļż’ż▒żŪżŽż╩żżż½żķĪóÖCĢ■ż¼ŲĮĄ╚żŪżóżļż╚żŽčįżżżŁżņż╩żżĪŻ 4 ż╔ż¾ż╩Ė▀ąŻ╔·żŪżŌųĖČ©ąŻż╬┤¾īWż“╩▄“Yż╣żļż│ż╚żŽżŪżŁżļż¼ĪóųĖČ©ąŻųŲČ╚ż╬┤µį┌żŽż█ż╚ż¾ż╔ų¬żķż╩żżż└żĒż”ż½żķĪóÖCĢ■ż¼ŲĮĄ╚żŪżóżļż╚żŽčįżżżŁżņż╩żżĪŻå¢5ĪĪ╣Pš▀ż¼ż│ż╬╬─š┬żŪūŅżŌčįżżż┐żżż│ż╚żŽĪóż╔żņż½ĪŻ 1 ż╣ż┘żŲż╬╚╦ķg╗Ņäėż╦ŲĮĄ╚ż¼▒ŻšŽżĄżņżŲżżżļż’ż▒żŪżŽż╩żżż¼ĪóĘ©ż╬Ž┬żŪż╬╚╦ķgż╬ŲĮĄ╚żŽæŚĘ©żŪżŌ▒ŻšŽżĄżņż┐╚╦ķgż╬╗∙▒ŠĄ─ż╩śž└¹żŪżóżĻĪóūųžżĄżņżļż┘żŁżŪżóżļĪŻ 2 ╚š▒ŠżŪżŽĪóć°├±ż╬╦∙Ą├╦«£╩ż¼Ž“╔ŽżĘż┐ż│ż╚ż╦żĶż├żŲĪó┬ÜśIĪóĮ╠ė²żõ╦∙Ą├ż╦ķvż╣żļ▓╗ŲĮĄ╚ż╬å¢Ņ}ż¼£pż├żŲżŁż┐ż¼Īó╔ńĢ■Ą─・├±ūÕĄ─▓Ņäeż╬å¢Ņ}ż¼┤¾żŁż»ż╩ż├żŲżżżļĪŻ 3 ÖCĢ■ż╬ŲĮĄ╚żŽč}ļjżŪīg█`ż╬ļyżĘżżįŁ└Ēż└ż¼Īó┬ÜśIżõĮ╠ė²ż╦ķvż╣żļ╗Ņäėż╦ż¬żżżŲż╣ż┘żŲż╬╚╦ż╦ŲĮĄ╚ż╩ÖCĢ■ż¼┼cż©żķżņżļż┘żŁżŪżóżļż│ż╚ż“═³żņżŲżŽż╩żķż╩żżĪŻ 4 ¼F┤·╔ńĢ■żŽ╗∙▒ŠĄ─ż╦ĖéĀÄ╔ńĢ■żŪżóżļż½żķĪóĖéĀÄż╬ĮY╣¹Īóä┘š▀ż╚öĪš▀ż╦Ęųż½żņĪóä┘š▀ż╦żŌĒś╬╗ż¼ż─ż▒żķżņżļż│ż╚żŽżõżÓż“ż©ż╩żżĪŻ å¢Ņ}ó¶ĪĪ┤╬ż╬╬─ż╬ĪĪĪĪĪĪĪĪż╦żŽż╔ż¾ż╩čį╚~ż¼╚ļżņż┐żķżĶżżż½ĪŻ1・2・3・4ż½żķūŅżŌ▀m«öż╩żŌż╬ż“ę╗ż─▀xżėż╩żĄżżĪŻ (1)ĪĪż’ż¼╔ńżŽīWÜsż╦ĪĪĪĪĪĪĪĪ▒Š╚╦ż╬īg┴”żŪƱė├ż“øQżßżŲżżżļĪŻĪĪ1ĪĪżĶżķż║ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż─ż½ż║ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż─żżżŲĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪżĶż├żŲ (2)ĪĪż╔ż¾ż╩ŽÓ╩ųżŪżŌĪóįć║Žż¼ĮKż’żļż▐żŪżŽę╗╦▓ĪĪĪĪĪĪĪĪė═öÓż¼żŪżŁż╩żżĪŻĪĪ1ĪĪżąż½żĻż½ĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż┐żĻż╚żŌĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż╩żķżŪżŽĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż╔ż│żĒż½ (3)ĪĪĢ■╔ńż╬įu┼ąĪĪĪĪĪĪĪĪż½żķĪóčuŲĘż╬ŲĘ┘|╣▄└ĒżŽģŚżĘż»żĘż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżĪŻĪĪ1ĪĪż“ż½ż«żļĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż╦żżż┐żļĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż“żßż░żļĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż╦ż½ż½ż’żļ (4)ĪĪ¤o┴ŽżŪė│«ŗż¼ęŖżķżņżļĪĪĪĪĪĪĪĪĪó╚ļżĻ┐┌ż╬Ū░ż╦żŽ1ĢrķgżŌŪ░ż½żķąą┴ąż¼żŪżŁż┐ĪŻĪĪ1ĪĪż╚żóż├żŲĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż╚żóż├żŲżŌĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż╚ż╣żļż╚ĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż╚żĄżņżŲżŌ (5)ĪĪ╩╦╩┬ż¼╔Įż╬żĶż”ż╦żóż├żŲĪó╚šĻū╚šĪĪĪĪĪĪĪĪĪó│÷╔ńżĘż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżĪŻĪĪ1ĪĪż╦żĮż├żŲĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż╚żŌż╩ż»ĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż╚żŽżżż©ĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż╦żĮż»żĘżŲ (6)ĪĪż½ż┐ż┼ż▒żļĪĪĪĪĪĪĪĪūėż╔żŌż¼ż¬żŌż┴żŃż“╔óżķż½ż╣ż╬żŪĪóżżżõż╦ż╩ż├żŲżĘż▐ż”ĪŻĪĪ1ĪĪżóż╚żŪżŽĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪżĮżąż½żķĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪżĶżĮż╦żŽĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż│ż╚ż▐żŪ (7)ĪĪż│ż╬ūėżŽąĪīW╔·ĪĪĪĪĪĪĪĪż║żżżųż¾żĘż├ż½żĻżĘżŲżżżļĪŻĪĪ1ĪĪż╦żĘżŲżŽĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż╦ż╣żļż╚ĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż╦ż╣żļż½żķĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż╦żĘżŲż½żķ (8)ĪĪžÜżĘżżĪĪĪĪĪĪĪĪ╩«Ęųż╩Į╠ė²ż“╩▄ż▒żķżņż╩żż╚╦Ī®ż¼żżżļĪŻĪĪ1ĪĪżŌż╬ż½żķĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż¼żµż©ż╦ĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż╚ż╣żļż╚ĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż’ż▒żŌż╩ż» (9)ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪż╦żĶż├żŲżŽĪóżĮż╬╩╦╩┬żŽżŌż├ż╚║åģgż╦£gż▐ż╗żļż│ż╚ż¼żŪżŁżļĪŻĪĪ1ĪĪżõżĻż½ż▒ĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪżõżĻżĮż”ĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪżõżĻżĶż”ĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪżõżĻż¼ż┴ (10)ĪĪėHż╦ĮU£gĄ─ż╩žōō·ż“ĪĪĪĪĪĪĪĪżĘżŲźóźļźąźżź╚żŪ╔·╗Ņ┘Mż“╝┌żżż└ĪŻĪĪ1ĪĪż½ż▒ż║ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż½ż▒ż─ż─ĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż½ż▒żĶż”ż╚ĪĪ
żŲĪó「╩▄“YæķĀÄ」ż“┐ŽČ©ż╣żļÜ▌żŽż╩żżĪŻŻ©ųą┬įŻ®▀^┐ßż╩「╩▄“YæķĀÄ」ż╦żŽžōż╬é╚├µż¼ČÓżżż╬żŪĪóæķĀÄż“ż╩ż»ż╣żļ▒žę¬ąįżŽĖ▀żżĪŻĪĪż╚ż│żĒżŪĪó╠žČ©┤¾īWęį═Ōż╬īW╔·ż╦ż╚ż├żŲżŽĪóŠ═┬Üįć“Yż╬ÖCĢ■ż¼ūŅ│§ż½żķ┼┼│²żĄżņżŲżżżļż╬żŪĪóÖCĢ■ż╬▓╗ŲĮĄ╚ż╚ė│żļż½żŌżĘżņż╩żżĪŻ┤_ż½ż╦żĮż╬é╚├µż¼żóżļż│ż╚żŽĘ±Č©żĘż©ż╩żżż¼ĪóżĶż»┐╝ż©żļż╚żĮż╬╚╦▀_ż╦żŌ╠žČ©ż╬┤¾īWż╬╩▄“Yż╬ÖCĢ■ż¼Ė▀ąŻ╔·ż╬Ģrż╦żóż├ż┐ż’ż▒żŪĪóÖCĢ■ż╬ŲĮĄ╚ż¼═Ļ╚½ż╦┼┼│²żĄżņżŲżżż┐ż╚żŽżżż©ż╩żżĪŻīgļHż╦żĮż╬┤¾īWż“╩▄“YżĘż┐ż½ż╔ż”ż½żŽå¢Ņ}żŪżŽż╩żżĪŻżĘż½żĘĖ▀ąŻ╔·ż╦ż▐żŪŲ¾śIż╦ųĖČ©ąŻųŲČ╚ż¼żóżļż│ż╚ż“ų¬ż├żŲżżżļĪóż╚Ų┌┤²ż╣żļż╬żŽ┐ßżŪżóżļĪŻÖCĢ■ż╬ŲĮĄ╚ż“ż│ż╬żĶż”ż╦┐╝ż©żŲż▀żļż╚ĪóęŌ═Ōż╦č}ļjż╩įŁ└Ēż╩ż╬żŪżóżļĪŻĪĪÖCĢ■Š∙Ą╚ż╬įŁ└Ēż“īg╩®ż╣żļż│ż╚żŽ╚▌ęūżŪżŽż╩żżż¼Īó└ĒŽļż╚żĘżŲ│Żż╦─ŅŅ^ż╬ż¬ż½żņżļż┘żŁįŁ└ĒżŪżóżļĪŻż╣ż┘żŲż╬ęŌė¹ż╬żóżļ╚╦ż╦żŽĪóģó╝ėż╚ĖéĀÄż╬ÖCĢ■ż¼┼cż©żķżņżļż│ż╚ż¼═¹ż▐żĘżżĪŻĮ╠ė²ż╬ÖCĢ■Īó╩╦╩┬ż╬ÖCĢ■ĪóŠ═┬Üż╬ÖCĢ■ĪóĢN▀Mż╬ÖCĢ■Īó╚╦╔·╔Žż╬śöśöż╩╗Ņäėż╦ż¬żżżŲČÓż»ż╬╚╦ż╦ŲĮĄ╚ż╩ÖCĢ■ż¼┼cż©żķżņż┐─®ż╦Īóģó╝ėš▀ż¼Ėéżż║Žż”ż│ż╚ż╚ż╩żļĪŻĖéĀÄż╬ĮY╣¹ä┘š▀ż╚öĪš▀ż¼│÷żļż│ż╚żŽ╩╦ĘĮż¼ż╩żżż│ż╚ż└żĘĪóä┘š▀ż╦żŌĒś╬╗ż┼ż▒ż¼ąąż’żņżļż│ż╚żŌżõżÓż“ż©ż╩żżĪŻ å¢1ĪĪĄ┌2Č╬┬õż╬ā╚╚▌ż╚║Žż├żŲżżżļżŌż╬żŽĪóż╔żņż½ĪŻ 1 ╚š▒ŠżŪżŽėHż╬ĮU£g┴”ż¼Ė▀ż»ż╩żżż┐żßż╦ūė╣®ż¼▀MīWżŪżŁż╩żżź▒®`ź╣żŽ£pż├żŲżŁżŲżżżļĪŻ 2 ╚š▒ŠżŪżŽėHż╬ĮU£g┴”ż¼Ė▀ż»ż╩żżż┐żßż╦ūė╣®ż¼▀MīWżŪżŁż╩żżź▒®`ź╣ż¼ę└╚╗ż╚żĘżŲČÓżżĪŻ 3 źóźßźĻź½żŪżŽÖCĢ■ż╬ŲĮĄ╚ż¼ųžęĢżĄżņżļż¼ĪóŖXīWĮųŲČ╚żŽ╚š▒Šż█ż╔│õīgżĘżŲżżż╩żżĪŻ 4 źóźßźĻź½żŪżŽÖCĢ■ż╬ŲĮĄ╚ż¼╚š▒Šż█ż╔ųžęĢżĄżņż╩żżż¼ĪóŖXīWĮųŲČ╚żŽ│õīgżĘżŲżżżļĪŻå¢2ĪĪųĖČ©ąŻųŲČ╚ż╬╠žÅšż╚żĘżŲĪó╣Pš▀ż╬šh├„ż╚║Žż”żŌż╬żŽż╔żņż½ĪŻ 1 ╠žČ©ż╬┤¾īWż╬ūõśI╔·ż└ż▒ż¼żĮż╬Ų¾śIżŪāPż»żĶż”ż╦ż╩żļż┐żßĪóŲ¾śIż╦īØżĘżŲųęīgż╩╔ńåTż“ēłżõż╣ż│ż╚ż¼żŪżŁżļĪŻ 2 ČÓż»ż╬īW╔·ż╬ųąż½żķ▀xżųż│ż╚ż╦ż╩żļż┐żßĪóŲ¾śIżŽ╚ļ╔ńßßż╣ż░ż╦│╔╣¹ż“╔Žż▓żķżņżļ╚╦ż“ęŖż─ż▒żļż│ż╚ż¼żŪżŁżļĪŻ 3 ╠žČ©ż╬┤¾īWęį═Ōż╬īW╔·żŽĪóÅĻ─╝ż╣żļļHż╦įć“Yż“╩▄ż▒ż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżż┐żßĪóę╗Č©ż╬╗∙£╩ęį╔Žż╬╚╦ż“▀xżųż│ż╚ż¼żŪżŁżļĪŻ 4 ā׹ѿ╩īW╔·ż¼żżżļż╚┐╝ż©żķżņżļ┤¾īWż╬īW╔·ż└ż▒ż¼ÅĻ─╝żŪżŁżļż┐żßĪóŲ¾śIżŽĄ═żżź│ź╣ź╚żŪ▀m«öż╩╚╦ż“▀xżųż│ż╚ż¼żŪżŁżļĪŻå¢3ĪĪĪĖżĮż╬╚╦▀_Ī╣ż╚żŽĪóż╔ż╬żĶż”ż╩╚╦ż“ųĖżĘżŲżżżļż½ĪŻ 1ĪĪ┤¾īW╩┌śIż“żĘż╩ż½ż├ż┐Ė▀ąŻ╔· 2ĪĪŲ¾śIż╬Ʊė├įć“Yż╦ÅĻ─╝żĘżŲż»żļż╣ż┘żŲż╬īW╔· 3 Ų¾śIż¼╩▄“Y・├µĮėż╬ÖCĢ■ż“┼cż©żŲżżż╩żż┤¾īWż╬īW╔· 4 Ų¾śIż¼╩▄“Y・├µĮėż╬ÖCĢ■ż“┼cż©żŲżżżļ╠žČ©┤¾īWż╬īW╔·å¢4ĪĪĖ▀ąŻż╬ļAČ╬ż╦ż▐żŪżĄż½ż╬ż▄ż├żŲ┐╝ż©ż┐ł÷║ŽĪóųĖČ©ąŻųŲČ╚ż╚ÖCĢ■ż╬ŲĮĄ╚ż╦ż─żżżŲ╣Pš▀żŽż╔ż╬żĶż”ż╦įuü²żĘżŲżżżļż½ĪŻ 1 Ė▀ąŻ╔·ż¼ųĖČ©ąŻųŲČ╚ż¼ż╩ż»ż╩żļż│ż╚ż“Ų┌┤²ż╣żļżŽż║ż¼ż╩żżż½żķĪóÖCĢ■ż╬▓╗ŲĮĄ╚żŽżĮżņż█ż╔┤¾żŁż╩å¢Ņ}żŪżŽż╩żżĪŻ 2 Ė▀ąŻ╔·żŽųĖČ©ąŻųŲČ╚ż¼żóżļż│ż╚ż“ų¬ż├ż┐ż”ż©żŪ┤¾īWż“╩▄“YżĘżŲżżżļż╬ż└ż½żķĪóÖCĢ■ż╬▓╗ŲĮĄ╚żŽżĮżņż█ż╔┤¾żŁż╩å¢Ņ}żŪżŽż╩żżĪŻ 3 ż╔ż¾ż╩Ė▀ąŻ╔·żŪżŌųĖČ©ąŻż╬┤¾īWż“╩▄“Yż╣żļż│ż╚żŽżŪżŁżļż¼Īóż╣ż┘żŲż╬╩▄“Y╔·ż¼║ŽĖ±żŪżŁżļż’ż▒żŪżŽż╩żżż½żķĪóÖCĢ■ż¼ŲĮĄ╚żŪżóżļż╚żŽčįżżżŁżņż╩żżĪŻ 4 ż╔ż¾ż╩Ė▀ąŻ╔·żŪżŌųĖČ©ąŻż╬┤¾īWż“╩▄“Yż╣żļż│ż╚żŽżŪżŁżļż¼ĪóųĖČ©ąŻųŲČ╚ż╬┤µį┌żŽż█ż╚ż¾ż╔ų¬żķż╩żżż└żĒż”ż½żķĪóÖCĢ■ż¼ŲĮĄ╚żŪżóżļż╚żŽčįżżżŁżņż╩żżĪŻå¢5ĪĪ╣Pš▀ż¼ż│ż╬╬─š┬żŪūŅżŌčįżżż┐żżż│ż╚żŽĪóż╔żņż½ĪŻ 1 ż╣ż┘żŲż╬╚╦ķg╗Ņäėż╦ŲĮĄ╚ż¼▒ŻšŽżĄżņżŲżżżļż’ż▒żŪżŽż╩żżż¼ĪóĘ©ż╬Ž┬żŪż╬╚╦ķgż╬ŲĮĄ╚żŽæŚĘ©żŪżŌ▒ŻšŽżĄżņż┐╚╦ķgż╬╗∙▒ŠĄ─ż╩śž└¹żŪżóżĻĪóūųžżĄżņżļż┘żŁżŪżóżļĪŻ 2 ╚š▒ŠżŪżŽĪóć°├±ż╬╦∙Ą├╦«£╩ż¼Ž“╔ŽżĘż┐ż│ż╚ż╦żĶż├żŲĪó┬ÜśIĪóĮ╠ė²żõ╦∙Ą├ż╦ķvż╣żļ▓╗ŲĮĄ╚ż╬å¢Ņ}ż¼£pż├żŲżŁż┐ż¼Īó╔ńĢ■Ą─・├±ūÕĄ─▓Ņäeż╬å¢Ņ}ż¼┤¾żŁż»ż╩ż├żŲżżżļĪŻ 3 ÖCĢ■ż╬ŲĮĄ╚żŽč}ļjżŪīg█`ż╬ļyżĘżżįŁ└Ēż└ż¼Īó┬ÜśIżõĮ╠ė²ż╦ķvż╣żļ╗Ņäėż╦ż¬żżżŲż╣ż┘żŲż╬╚╦ż╦ŲĮĄ╚ż╩ÖCĢ■ż¼┼cż©żķżņżļż┘żŁżŪżóżļż│ż╚ż“═³żņżŲżŽż╩żķż╩żżĪŻ 4 ¼F┤·╔ńĢ■żŽ╗∙▒ŠĄ─ż╦ĖéĀÄ╔ńĢ■żŪżóżļż½żķĪóĖéĀÄż╬ĮY╣¹Īóä┘š▀ż╚öĪš▀ż╦Ęųż½żņĪóä┘š▀ż╦żŌĒś╬╗ż¼ż─ż▒żķżņżļż│ż╚żŽżõżÓż“ż©ż╩żżĪŻ å¢Ņ}ó¶ĪĪ┤╬ż╬╬─ż╬ĪĪĪĪĪĪĪĪż╦żŽż╔ż¾ż╩čį╚~ż¼╚ļżņż┐żķżĶżżż½ĪŻ1・2・3・4ż½żķūŅżŌ▀m«öż╩żŌż╬ż“ę╗ż─▀xżėż╩żĄżżĪŻ (1)ĪĪż’ż¼╔ńżŽīWÜsż╦ĪĪĪĪĪĪĪĪ▒Š╚╦ż╬īg┴”żŪƱė├ż“øQżßżŲżżżļĪŻĪĪ1ĪĪżĶżķż║ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż─ż½ż║ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż─żżżŲĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪżĶż├żŲ (2)ĪĪż╔ż¾ż╩ŽÓ╩ųżŪżŌĪóįć║Žż¼ĮKż’żļż▐żŪżŽę╗╦▓ĪĪĪĪĪĪĪĪė═öÓż¼żŪżŁż╩żżĪŻĪĪ1ĪĪżąż½żĻż½ĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż┐żĻż╚żŌĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż╩żķżŪżŽĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż╔ż│żĒż½ (3)ĪĪĢ■╔ńż╬įu┼ąĪĪĪĪĪĪĪĪż½żķĪóčuŲĘż╬ŲĘ┘|╣▄└ĒżŽģŚżĘż»żĘż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżĪŻĪĪ1ĪĪż“ż½ż«żļĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż╦żżż┐żļĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż“żßż░żļĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż╦ż½ż½ż’żļ (4)ĪĪ¤o┴ŽżŪė│«ŗż¼ęŖżķżņżļĪĪĪĪĪĪĪĪĪó╚ļżĻ┐┌ż╬Ū░ż╦żŽ1ĢrķgżŌŪ░ż½żķąą┴ąż¼żŪżŁż┐ĪŻĪĪ1ĪĪż╚żóż├żŲĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż╚żóż├żŲżŌĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż╚ż╣żļż╚ĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż╚żĄżņżŲżŌ (5)ĪĪ╩╦╩┬ż¼╔Įż╬żĶż”ż╦żóż├żŲĪó╚šĻū╚šĪĪĪĪĪĪĪĪĪó│÷╔ńżĘż╩ż▒żņżąż╩żķż╩żżĪŻĪĪ1ĪĪż╦żĮż├żŲĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż╚żŌż╩ż»ĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż╚żŽżżż©ĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż╦żĮż»żĘżŲ (6)ĪĪż½ż┐ż┼ż▒żļĪĪĪĪĪĪĪĪūėż╔żŌż¼ż¬żŌż┴żŃż“╔óżķż½ż╣ż╬żŪĪóżżżõż╦ż╩ż├żŲżĘż▐ż”ĪŻĪĪ1ĪĪżóż╚żŪżŽĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪżĮżąż½żķĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪżĶżĮż╦żŽĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż│ż╚ż▐żŪ (7)ĪĪż│ż╬ūėżŽąĪīW╔·ĪĪĪĪĪĪĪĪż║żżżųż¾żĘż├ż½żĻżĘżŲżżżļĪŻĪĪ1ĪĪż╦żĘżŲżŽĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż╦ż╣żļż╚ĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż╦ż╣żļż½żķĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż╦żĘżŲż½żķ (8)ĪĪžÜżĘżżĪĪĪĪĪĪĪĪ╩«Ęųż╩Į╠ė²ż“╩▄ż▒żķżņż╩żż╚╦Ī®ż¼żżżļĪŻĪĪ1ĪĪżŌż╬ż½żķĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż¼żµż©ż╦ĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż╚ż╣żļż╚ĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪż’ż▒żŌż╩ż» (9)ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪż╦żĶż├żŲżŽĪóżĮż╬╩╦╩┬żŽżŌż├ż╚║åģgż╦£gż▐ż╗żļż│ż╚ż¼żŪżŁżļĪŻĪĪ1ĪĪżõżĻż½ż▒ĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪżõżĻżĮż”ĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪżõżĻżĶż”ĪĪĪĪĪĪĪĪ4ĪĪżõżĻż¼ż┴ (10)ĪĪėHż╦ĮU£gĄ─ż╩žōō·ż“ĪĪĪĪĪĪĪĪżĘżŲźóźļźąźżź╚żŪ╔·╗Ņ┘Mż“╝┌żżż└ĪŻĪĪ1ĪĪż½ż▒ż║ĪĪĪĪĪĪĪĪĪĪ2ĪĪż½ż▒ż─ż─ĪĪĪĪĪĪĪĪ3ĪĪż½ż▒żĶż”ż╚ĪĪ


